~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
~消滅時効の援用で失敗しないために知っておきたいこと~
国民健康保険は、自営業者や高齢者が加入する保険です。
国民が公的医療保険に加入し、保険料を負担する代わりに、個人にかかる医療費を軽減する目的があります。
しかし、社会保険料に比べると国民健康保険料は割高であるため、支払いを負担に思っている方も多いのではないでしょうか。
国民健康保険を滞納すると、段階的に保険証が切り替わります。病院に行くと窓口負担が増えるため、実質、健康保険がない状態になります。
ここでは、国民健康保険を滞納するとどうなるのかについて、段階的に紹介します。
国民健康保険料の滞納が1年未満の場合、有効期限が3ヶ月〜6ヶ月と短く設定されている健康保険証が交付されます。
有効期限が短く、頻繁に更新が必要な短期被保険者証と呼ばれるもので、頻繁に更新手続きが必要な点が特徴です。
保険証の更新をするたびに、役所の担当者に会わなくてはならず、保険料の支払いを催促されます。
短期被保険者証を提示すると、病院での窓口負担は3割です。
特別な理由も無く国民健康保険料を滞納して1年以上が経過すると、短期被保険者証の返納を求められます。代わりに配布されるのが、被保険者資格証明書です。
被保険者資格証明書を病院の窓口に提示すると、窓口負担は一気に10割負担になります。つまり、保険証を持っていないのと同様の扱いになるわけです。
役所にて手続きをすれば、後日医療費の7割は返還されますが、滞納している保険料と相殺されるため、手取りはありません。
被保険者資格証明書を持っていても、保険証の役割は果たさないため、病院に行きづらくなると感じる方が増えるはずです。
1年6ヶ月以上、国民健康保険料を滞納していると、保険給付の差し止めが行われます。病院の窓口負担は10割で、還付金は自動的に国民健康保険料に充当されます。
1年6ヶ月を過ぎると、差し押さえ通知が届くようになり、給与や車などの財産は差し押さえられる可能性が高くなるため、理解しておきましょう。
国民健康保険料が支払えなくなったら、そのまま放置してはいけません。
すぐに国民年金課に電話して相談すると、保険料の軽減や減免が受けられる可能性があります。
ここでは、国民健康保険料を軽減・減免する手続きについて紹介します。
一定の所得以下の方は、国民健康保険料の軽減措置が受けられる可能性があります。前年度の所得が政令で定められている基準額以下の世帯に対して、保険料の7割・5割・2割が減額されます。
また、会社の倒産や解雇などで職を失った、非自発的離職者が保険料の軽減を受けるには、届出が必要です。
軽減の制度は住んでいる市町村区によって制度が異なるため、確認が必要です。
所得が減り、保険料の支払いが困難になった場合は、保険料の減免が受けられる可能性があります。
また、令和3年度からは中学生以下の子どもが2名いる世帯に対して、多子世帯減免が適用されています。
保険料の減免が受けられる条件は以下のとおりです。
保険料の減免を受けるには、該当年度内に申請をしなければなりません。
減免の制度は住んでいる市町村区によって制度が異なるため、確認が必要です。
国民健康保険料の支払いにも時効はあります。しかし、時効の完成は非常に難しいと言われています。
ここでは、国民健康保険料の時効について紹介します。
国民健康保険料を支払っている方には、国民健康保険法が適用され、時効期間は2年と定められています。
保険料が未払いの場合、すぐに債権者からの催促が始まり、催促が続いている間は時効はストップしたままです。
常に時効期間は更新され続けるので、消滅時効はありえません。
督促がないまま2年間を経過すれば時効の成立は期待できますが、現実には督促は継続され、延滞料や滞納額が増えるだけです。
国民健康保険税を支払っている方は、地方税法が適用され、時効期間は保険料の支払い期限日の翌日から5年間です。
保険料と同じく、督促がある間は、時効は更新され続けます。そのため、時効が成立するのは考えにくいといわれています。
保険税の未払いのために差し押さえが実行されると、解除されるまで時効はストップしたままです。
また、保険税を分割で支払っている場合は、時効は進まないままで、再び滞納が始まった翌日から5年以上経過しないと時効はありえません。
国民健康保険料を未払いのまま時効を成立させるのが難しいといわれる理由には、以下のようなものがあります。
国民健康保険は加入すると納付義務が発生するため、自己破産をしても生活保護世帯になっても支払わなければなりません。
徴収が厳しい一方で、支払い方法を分割にしたり、延滞料の減額に応じてもらえたりと臨機応変に対応してもらえる面もあります。
国民健康保険を滞納しておくのはリスクが大きいといわれています。
ここでは、滞納するとどのようなリスクがあるのかについて紹介します。
支払いを滞納しており、督促状に記載されている期限までに国民健康保険料の納付ができなかった場合は、年率3.8%〜14.6の延滞料が課せられます。
年率に幅があるのは、本来の支払日の翌日から3ヶ月の間は年率3.8%で、4ヶ月目からは14.6%の年率で計算するからです。
国民健康保険を滞納し続けていると、最終的に給与・不動産など財産の差し押さえに発展します。
給与は全額が差し押さえられるわけではありませんが、滞納している金額が返済し終わるまで継続されます。
不動産が差し押さえられた場合、土地・建物・マンションなどは負債者が自由に売買できません。
差し押さえは、督促状の発行から10日待っても支払いがなされない場合は実行が可能です。
国民健康保険の税額は、前年の所得と住んでいた市町村によって異なります。昨年と税額が異なるのは、所得割、均等割、平等割の合計額で算出しており、所得額が変わっていたり、世帯人数が変わったりすると保険税の金額が変わる可能性があります。
また、国民健康保険は、2018年より各都道府県の運営となったため、地域別に国保加入車の医療費から税率を算出しているためです。
地域差は大きく、場所によっては1.4倍もの差が生じる場合もあります。
国民健康保険は滞納してもリスクばかりで、メリットになるものはありません。
保険証を持っていないのと同様の状況に追い込まれ、病気すらできない状態になるため、1日でも早く支払いをするのが賢明といえるでしょう。
時効は2年と定められていますが、督促状が届き続ける限り時効は成立しません。国民健康保険の滞納以外にも、金銭的に困窮している場合は、ぜひ専門家に相談をしてください。
借金が軽減できると生活にも余裕が出て、前向きになれるはずです。
国民健康保険の滞納を1日でも早く改善し、金銭的にも精神的にも安定した日々を取り戻しましょう。
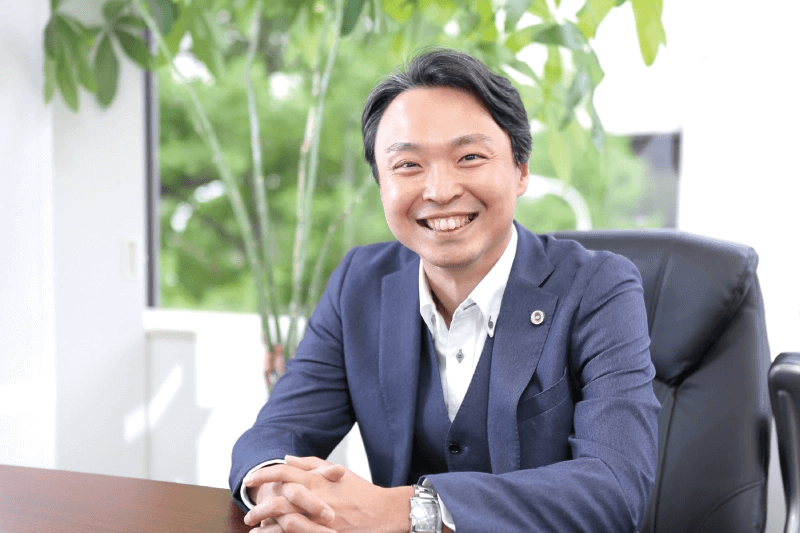
引用元:東京スカイ法律事務所公式HP(https://www.tsky.jp/)
代表弁護士:田中 健太郎 先生
法律相談件数が20,000件を超える実績(2023年8月時点)がある東京スカイ法律事務所では、【借金問題の相談無料】という相談者にとって非常に助かるサービスを提供しています。
東京に居を構える弁護士事務所ですが、地方からの相談にも対応しており誰からの相談にも真摯に応えてくれる頼れる弁護士事務所となります。
借金相談無料
土日相談可
電話相談可
メール相談可
※債務整理(個人破産・法人破産・個人再生・任意整理・過払金の回収)・相続・住宅ローン・時効援用・立退きに関する相談は無料です。その他の法律相談は、30分5500円(税込)になります。
※記載している実績は2023年8月調査時点での情報となります。
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区京橋二丁目12-9 ACN京橋ビル601 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 連絡先TEL | 0120-0505-90 |
※選定基準:2023年6月20日時点でGoogle検索にて「時効の援用」で表示された全175件の中から弁護士事務所として表示された58社を調査、その中で公式サイト内で時効の援用に対応できることが明記されている弁護士事務所の中から29社を掲載しております。
借金の返済義務を無くすことができる手続き、時効の援用についてまとめているカテゴリーです。
貸主対応や失敗のリスクなど、時効の援用につきまとう不安を回避できる相談先を紹介。
借金の種類ごとに、未払い・滞納を放置するとどうなるか、どのくらいで時効になるか、解説しています。
時効の援用手続きには、大まかに分けて以下のような3つの種類があります。それぞれ詳しくまとめてみました。
債権回収会社とは何なのか、督促状などが送られてきた場合どう対応すべきか、まとめてみました。